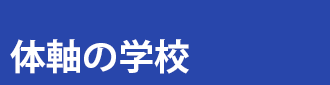バイオリンやチェロ等の弦楽器もイス軸法で音や動きが変わる!体軸で上達

バイオリンやチェロなど弦楽器(擦弦楽器)にイス軸法を取り入れるとどのような効果やメリットがあるか?体軸が整った状態でバイオリンやチェロなど弦楽器を弾くと音や演奏にどんな変化があるかを検証してみました。
- 音色に深みや豊かさを出したい
- 肩や首の緊張を解消して楽に演奏したい
- 長時間の練習や本番でも疲れにくくなりたい
- 左手の運指をより正確で滑らかにしたい
- 効率的に上達して表現力を高めたい
そんな方に向けて、この記事ではバイオリン演奏のパフォーマンスを劇的に向上させる「体軸」の重要性と、誰でも簡単に体軸を作れる「イス軸法」について紹介しています。
ボウイングの滑らかさ、音色の美しさ、左手指の精密な動き、演奏中の集中力維持、演奏家に多い肩こりや腱鞘炎などの予防まで—あなたのバイオリン人生をより豊かにする可能性を秘めた「体軸」を、イス軸法でぜひ体験してみてください。
バイオリンやチェロなど弦楽器(擦弦楽器)にイス軸法を取り入れたいと思っている方の参考になれば幸いです。(ギターやベースなど撥弦楽器はこちら)
※みんなの体軸教室では、東京都内のピアノやドラムがある会場、楽器を思いっきり演奏できる防音室のある会場や、カラオケルームでのパーソナルレッスンやグループレッスンも承っています。詳細は公式LINEにてお問合せください。
音楽家のための体験会
8/10(日)の朝10時から、板橋区の防音ルームのある施設で音楽家のための体験会を行います。
ピアノ・ドラムあり。楽器持込OK、吹奏楽や歌もOK
音楽体験会の詳細はこちら
イス軸法×弦楽器で体軸が安定するメリット
バイオリンやチェロなど弦楽器では、イス軸法で体軸が安定すると弦で弾く音が強く出せる、繊細な音など音の強弱が出しやすい、演奏時の姿勢が安定して楽になる、楽器の持ち運びも楽になるなどのメリットがあるようです。
弓の扱い方による音の変化や、弦の押さえ方の変化による弾きやすさ、バイオリンは姿勢が大事と言われますが、演奏時に良い姿勢を楽にキープしやすくなりますし、上半身を大きく動かしても安定した姿勢が維持しやすくなります。
バイオリンは左手を身体の構造上は不自然なくらいにねじった状態で演奏をするため、首や肩から手先まで力みが入りやすく、体軸があるかないかは大きく差が出やすいようです。
スケール練習やエチュード、フォームの改善はもちろん大切ですが、その土台となる「体の軸」を整えることで練習効果が高まって上達が早くなり、次のレベルにどんどん進めるようになり、肩こりや腱鞘炎などのバイオリン奏者によく見られる症状の予防にもつながります。
イス軸法を取り入れたらアマチュアからセミプロに、セミプロからプロフェッショナルな演奏家へのステップアップにつながるかもしれませんし、オーケストラや室内楽、四重奏・五重奏などで取り入れたら全体の演奏レベルアップにつながります。
- 姿勢が安定し、音程がブレにくくなる
軸が整うことで体がぐらつかず、指の位置や運弓の安定感が増し、音程の精度が格段に向上。 - 肩・首・腕に余計な力みがなくなり、ラクに長時間弾けるようになる
無意識の緊張が抜けて、体の負担が減り、自然にラクな演奏姿勢になる。 - 音がクリアになり、表現力が広がる
軸があるとボウイングが安定し、力まなくても深みのある音が出せるようになる。 - 楽器と自分の身体が一体化したような感覚が出てくる
軸の感覚を持つと、重心が安定し、バイオリンが“乗っている”ように感じられるように。 - 身体の使い方が整い、フォームが美しくなる
姿勢が整うことで、自然で美しい構えができ、鏡に映る姿にも自信が持てるようになる。 - 音を出す瞬間の集中力が増し、タッチが繊細になる
軸が通ると“今ここ”への意識が高まり、感覚の解像度が上がる。 - 身体の左右差やクセに気づきやすくなる
たとえば「左肩が上がっていた」「右手にばかり力が入っていた」など、自分で修正しやすくなる。 - 長時間の練習でも疲れにくくなり、練習の質と量が自然に増える
軸が通ることで、同じ時間でも集中力が持続し、練習後の疲労感が減る。 - 舞台や発表会でも堂々と演奏できるようになる
軸が整うことで“地に足がついた安心感”が得られ、緊張しにくくなる。 - 音にムラがなくなり、「安定感のある演奏」と評価されやすくなる
音の立ち上がり、音量、音の伸びが安定することで、聴く側の印象が大きく変わる。
イス軸法は5秒でできて効果がすぐに出るので、練習前に行うのはもちろん、コンサートや発表会の前などに行うのも効果的です。
バイオリンやチェロなど弦楽器にイス軸法を取り入れて体軸が安定するメリットをまずは紹介しました。
「ちょっと試してみようかな」と思った方はイス軸法のやり方をチェックしてみてください。
なお、実際に体験してみたい方や、正しくできているか心配な方はイス軸法の体験会の日程をチェックしておきましょう。
バイオリンの初心者にも効果がある?

イス軸法はバイオリンやチェロを始めたばかりの初心者のかたでもメリットがあります。
- 姿勢が安定し、構えが楽になる
軸が整うことでバイオリンを自然に支えられ、構えがラクに決まるようになる。 - 音程が安定し、きれいな音が出しやすくなる
ブレが減って指の位置が安定するため、正しい音程が取りやすくなる。 - 肩や首の疲れが減り、長く練習できるようになる
無理な力みが抜けて、体がリラックスした状態で演奏できる。 - 弓の動きが安定し、音が途切れにくくなる
軸が通っていると弓のコントロールがしやすく、なめらかな音が出せるようになる。 - 「弾けた!」という実感が得られやすくなる
体の安定により演奏が形になりやすく、達成感や楽しさを感じやすくなる。
などのメリットがあります。
上達スピードが早くなるのはバイオリンやチェロの初心者には嬉しいですよね。
特にきれいな音を出し続けるのが難しいというのは、弓を持つ手や指や肘・肩などの力みが抜けるほどやりやすくなっていきます。
早く上手くなれば憧れの難しい曲にも早く挑戦できたり、発表会やコンサートにも早く出れたりするかもしれません。
中上級者にもメリットはある?

もちろんバイオリンやチェロ中上級者のかたにもメリットがあります。
- 音の表現力が高まり、繊細なニュアンスがつけられるようになる
無駄な力みが抜け、必要な力を正確に伝えられるため、音に深みとコントロールが生まれる。 - 長時間演奏しても疲れにくくなる
軸のある体の使い方でエネルギーの消耗が減り、演奏中の集中力も持続しやすくなる。 - 音程や音質のムラが減り、安定感が増す
身体が軸で支えられることで、どのポジションでも安定した演奏ができる。 - 本番や発表会でも堂々とした演奏ができるようになる
軸が整うと心身が落ち着き、緊張の中でも自分らしい演奏がしやすくなる。 - 身体のクセや左右差に自分で気づけるようになる
軸を通すことで、「あれ?こっちに偏ってるな」と微調整ができるようになる。
これまで練習してきたことで、うまくいかないことは自分でも気づいていない身体の力みが原因のことが多いです。実際に体軸とは関係なさそうな指先の動きが良くなったという声はよく聞きます。軸が安定すると思わぬところで効果がより発揮されたりします。
バイオリンは左手の手首をねじった姿勢で演奏するため、体幹部から指先まで力みが発生しやすいです。その力みをいかに抜けるかは演奏の違いを分けるポイントになり、力みが抜けると一気にパフォーマンスが上がることも多いです。
バイオリンでのイス軸法のチェック方法
バイオリンでのイス軸法のチェック方法は、基本のチェック方法の他にこのようなチェックをしてみるのがおすすめです。
まずはイス軸法を行う前の普段の状態でチェックをします。
バイオリン演奏時の姿勢でチェック
基本の真っすぐ立つ姿勢のほかに、バイオリン演奏時の姿勢をチェックしてみます。
- バイオリン演奏時の姿勢をとる
- 前から胸骨のあたりをゆっくり押してもらう
- 後ろからもゆっくり押してもらう
- 押された状態での身体の安定感をチェックする
音や指使いのチェック
次は体軸ではなく自分の感覚のチェックです。弓を引いて音を出してみたり、左手の指使いを少しやってみてください。
- 弓を引いて音を出してみる(音色・肩や指の力の抜け具合)
- 左手の指使いを(簡単なもの・できるけどちょっと難しいくらいの指使い・できるときとできないときがあるくらいの難易度の指使い)
- 実際に演奏するように上半身を動かしてみる(動きやすさ・姿勢の乱れがないか)
次に、イス軸法を行った後に同じチェックをしてみましょう。動きやすさの変化、可動域、緊張や呼吸の変化を感じてみましょう。負荷チェックは同じ強さでチェックして強さの変化をみます。
イス軸法を弦楽器に取り入れるには

いかがでしたでしょうか?たった5秒でできるイス軸法でこういった効果が出ているってすごいですよね。
「ちょっと試してみようかな」と思った方はイス軸法のやり方をチェックしてみてください。まだ「本当かなぁ?」という人もいると思いますが、まずは試してみてください。
イス軸法を実際に体験してみたい方や、正しくできているか心配な方はインストラクターが指導するイス軸法の体験会や、正しく習得していくパーソナルレッスンやグループレッスンをチェックしてください。
イス軸法をバイオリン教室等のレッスンメニューに取り入れていい?
簡単にできて効果が高いのでバイオリン教室等の練習メニューに取り入れたいという先生もいるかもしれませんが、お金を取ってイス軸法を教えるのはインストラクターのみです。有料のレッスンの一部として教えることはできません。(無償で教えるのは大丈夫です)
みんなの体軸教室では、イス軸法インストラクターがグループレッスンで音楽教室等のイベントとして体験会を開催したり、パーソナルレッスンで大会やコンクールの前に会場で体軸調整もできますので、公式LINEにてお問い合わせください。
おまけ:大人が始めても上手くなる?
「バイオリンは小さい頃からやっていないと上手くならない」という言葉を聞いたことがある人も多いかもしれません。
これはあくまで仮説ではありますが、子供のうちはまだ体軸がある子が多いので、バイオリンを演奏するときの姿勢(身体の構造上不自然な姿勢が多い)でも、しっかりと安定感を持った状態を維持し、無自覚な体幹の力みや肩の力み、そこから派生する腕や指先の力みなどが生じにくいことが考えられます。
つまり、身体がリラックスして演奏できる状態でスタートで来ている。大人と子供では基本中の基本の姿勢のところで無自覚な力みの発生しやすさという差がついている可能性があるということです。
もちろん、子供のものごとの吸収力の高さや練習量などもありますが、「上手く」の基準をどこに持っていくかにもよります(3歳からやっている同い年の人のレベルはさすがに難しいかもしれません)。
「大人だから」上手くならないのではなく、(仕事などで)大人は練習量がとれないから、(いろんな固定観念で)大人は先生の言うことを素直に聞けないから、(コリや力みのクセがついていて)大人は身体をうまく扱えていないから、といった部分なのではないでしょうか。